目標を評価の対象としないでください。※毒ヘビが増えます!
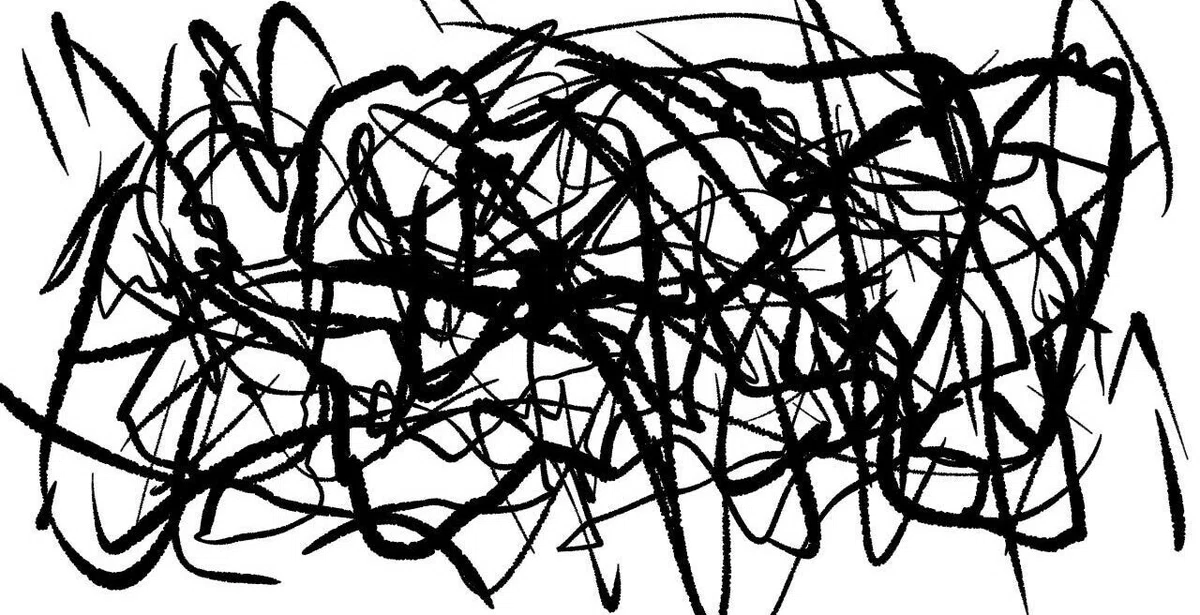
「結果がすべてだ」とは、ビジネスではよく耳にする言葉です。
目標となる売上や利益を設定し、それを達成するよう上司は部下に発破をかけます。
「今日は何件契約を獲得できたんだ」
「コスト削減は何パーセント進んでいるんだ」
部下には具体的な期限や数字を達成することが求められます。そしてたいていは、そういった目標の達成度合いが「人事評価の対象」となっています。
しかし、これらの取り組みはかえって部下のパフォーマンスを低下させ、不正行為や目の前の数字だけを達成させるような近視眼的な行動を誘発させてしまうことがあるのです。
コブラはなぜ増えた?
こんな話があります。
インドを統治していたインド総督府は、有害な毒ヘビのコブラを駆除することを目標に掲げ、コブラの死骸を持ってくれば報酬を与えると市民に伝えました。それによってみんなのモチベーションは高まったでしょうか。
答えは「イエス」です。
ではコブラは駆除できたのか。
答えは「ノー」です。
なぜなら報酬をもらうために、コブラを飼育する人々が現れたからです!
それを知った政府が慌ててこの制度を取りやめた後、そのコブラはどうなったかって?もちろん、いらなくなったコブラは野に放たれました。
パスは奪われなくなったのに…
もう一つ事例だけを紹介すると、
ニューヨークに本拠地を置くアメフトのニューヨーク・ジェッツのクォーターバックだったケン・オブライエンは、仲間にパスを出すときにボールが相手側に奪われることが課題でした。そこで、相手に奪われるパスを減らすという目標を設定し、もしパスが奪われたら罰金を支払うというルールを課せられました。結果どうなったのか。
目標どおり相手にパスを奪われることは減りました。ところが、それはパスの回数が減ったために過ぎず、パフォーマンスはむしろ下がってしまったのです!
誤った目標設定が目的を見失わせる
これらの事例は、すべて間違った目標設定により生じた弊害といえます。目の前の目標数字だけにとらわれて、本来の目的を見失ってしまったのです。目標数字はあくまで結果を測るためのモノサシであり、達成すべき目的ではないのです。
ところが、上から半ば強制的に目標が設定され、そこにインセンティブやペナルティなどの評価が与えられれば、近視眼的に目標を追いかけることになってしまいます。最悪は目標達成のために、不正を行う部下さえも現れてしまうかもしれません。
正しい目標設定の方法
では、どのように目標を設定することが適切なのか。
1つは、
目標を設定することの目的を理解させることです。
なぜ、なんのためにその目標数字を設定するのか、なにを目的としているのか…。一方的に上司が目標を設定するのではなく、目標を設定する段階から部下たちに関わらせるのです。
そして2つ目は、
目標数字を直接的に金銭的な人事評価と結びつけないことです。
目標が評価の対象となれば、意図していなくても評価を得るための手段に目標が入れ替わってしまうからです。
そんなことをしなくても、その目標の持つ意味をきちんと部下たちに伝え、結果をフィードバックすれば、おのずと目標達成に向けて行動するのです。
つまりは、目標を部下をコントロールするための手段につかってはいけないということです。そこを見誤れば、たちまち目標の弊害が起こってしまうのです。