南極遠征から学ぶ経営の極意!
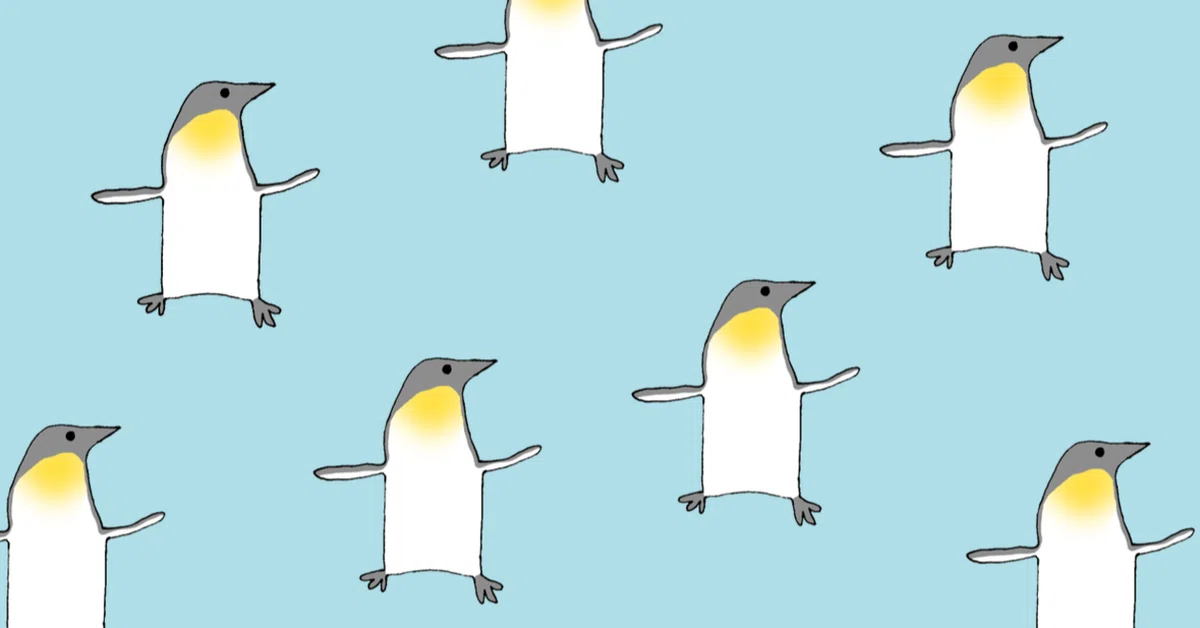
ノルウェーの冒険家ロアール・アムンセンとイギリスの軍人ロバート・スコットは、南極点到達とうい人類初の挑戦に国の威信をかけて競い合っていました。
1911年12月12日、アムンセンのチームは、南極点までわずか45マイル(およそ72㎞)という地点にまでせまっていました。その日は天候にも恵まれ、一気に進めば1日で南極点まで到達することも可能な距離です。ところが彼らが南極点に到達したのは、それから3日後の12月15日でした。
ライバルのスコットより先に進んでいるという確信はあったものの、いつ追いつかれるかわからない状況です。彼らになにかアクシデントでもあったのでしょうか?
毎日決まった距離だけ進む
アムンセンは出発したときから、毎日正確に15マイルずつ進むということを決めていました。雪が降ろうが晴れていようが関係ありません。まるで時計の針が時に刻むように、毎日きっかり15マイル確実に進むということを淡々と繰り返していたのです。
たとえ凍てつく寒さの厳しい日でも着実に歩みを進め、逆に晴れた穏やかな日に楽に15マイル進めたときは、そこで休息をとりました。その行動パターンは、ゴールを目の前にしたときでさえも決して変わらなかったのです。

極端なペース配分
一方スコットは、天候が穏やかな日にはこれでもかというほど無理な前進を進め、逆に天候が悪い日だけ休むというパターンでした。
ところがスコットのチームはその極端なペース配分に次第に疲弊しはじめます。歩く速度は落ち、南極点に到達したのはアムンセンに遅れること34日後でした。
先を越されたことに落胆した帰路の途中、さらに悲劇だったのは、ひどい凍傷と物資の不足からスコットを含む全員がその命を落としってしまったことです。
最初に飛ばしすぎてスタミナ切れになってしまい、その遅れを取り戻そうとまたオバーワークをすれば、ながく継続できないことは当たり前のことです。しかし、ほとんどの人がこのジレンマに陥ってしまうのです。
「年輪経営」
長野県にある「かんてんぱぱ」で有名な伊那食品工業は、48期連続で増収増益を続けてきました。その経営手法は、木の年輪の如くゆっくりと着実に成長する様子に例えて「年輪経営」と呼ばれています。
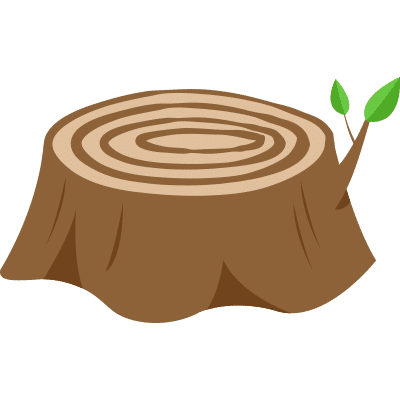
あるとき雑誌の記者から「毎年継続して成長し続けるコツはなんですか」と問われると、当時社長だった塚越寛氏は少し間をおいて「あまり売上を伸ばしすぎないことです」と答えました。その回答に質問した記者も思わず言葉を失ってしまいました。
しかし彼の言葉のとおり、伊那食品は周りがどんなに好景気で浮かれているときも決して無理な設備投資はせず、逆に景気が落ち込んでいるときでも攻めの姿勢を崩すことはありませんでした。
「どんなときでも着実に毎日前進し続ける」
これが成功のカギ(極意)なのです。