なぜ「頑張れ!」で社員が動かないのか?生産性1.5倍上げた秘訣
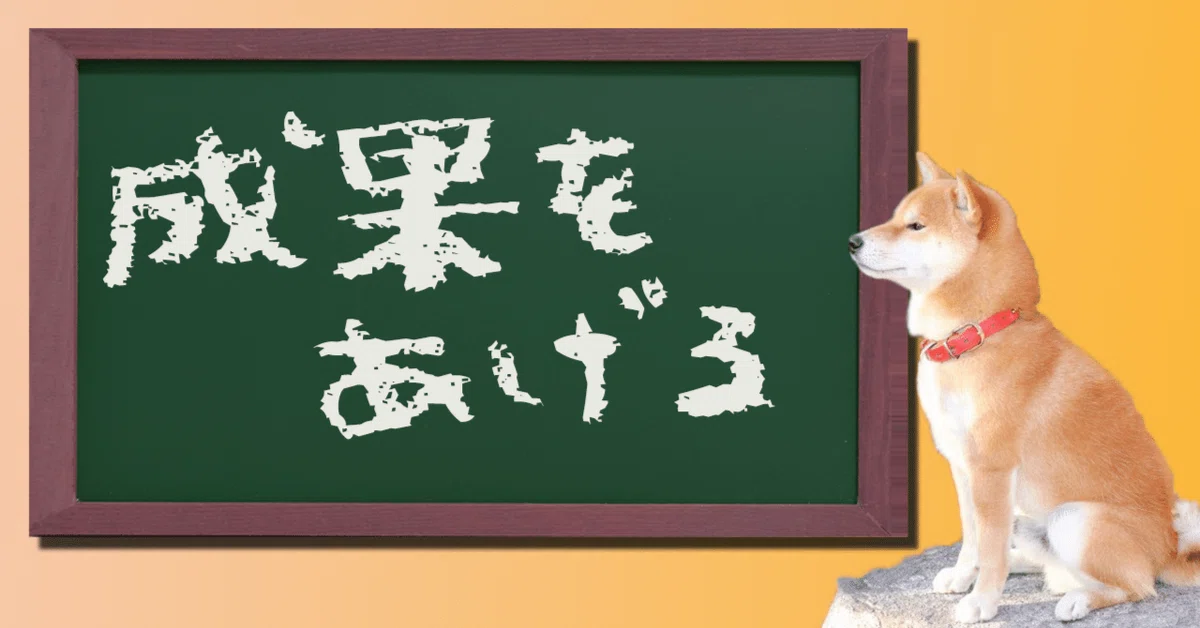
「とにかくやれることはなんでもやろう!」「1円でも多く利益を出そう!」。もし会社の経営が行き詰まっていたとしたら、そんなふうに社員の士気を高めようとするかもしれません。
しかし、これらの「ベストを尽くそう」という励まし方は、残念ながらあまり効果がないことが研究からわかっています。なぜなら、適切で具体的な目標が設定されていないからです。人の行動を促すには、数字で測れる明確な目標設定が必要なのです。
目次
- 劇手に生産性をあげた驚きの実験結果
- なぜ目標設定は行動を変えるのか?
- 組織を動かす具体的目標の力
劇手に生産性をあげた驚きの実験結果
目標設定理論を確立した著名な研究者であるゲイリー・レイサムとエドウィン・ロックは、製材所で働く木材トラックの積み込み作業者を対象に、どうすれば作業効率をもっと高められるか調査をしました。
研究者は作業者を二つのグループに分け、次のように指示しました。
1.目標設定グループ: 「今日は〇本の木材を積み込む」といった明確で具体的な作業目標を設定
2.目標を設定しないグループ: 具体的な目標は設定せず「ベストを尽くす」ことだけを要求
すると、明確で具体的な目標を設定したグループは、目標が曖昧だったり「ベストを尽くす」だけだったグループに比べ、はるかに多くの木材を積み込むことができました。
具体的には、トラックの積載可能な最大容量に対して約60%前後だった積み込み量が、積載容量の約90%まで改善しました。その差はなんと1.5倍です。作業効率を1.5倍も向上させることがどれだけ難しいかは、経営をされた方ならよくわかると思います。しかし、目標設定を具体的に「〇本積み込む」「〇%積み込む」と変えただけで、劇的な変化をもたらしたのです。
なぜ目標設定は行動を変えるのか?
なぜこれほどまでの改善をもたらすことができたのでしょうか。 いくつか理由は考えられますが、その一つは「意識が明確化された」ということです。
ただ「ベストを尽くせ」という目標では、どのように行動すればよいのか具体的なイメージが浮かびません。 しかし、具体的な数値が示されれば、それを達成するためにどう行動すればよいか、どのように改善すればよいかという具体的な行動に意識を向けることができます。
数値が明確であれば、後から達成度合いを検討することも可能です。そうすれば、さらなる改善策も検討できるでしょう。設定する数値も単なる「売上」より「何本積む」「何個売る」のような行動につながる数値の方がより効果的です。
組織を動かす具体的目標の力
取り組むべきことが明確になれば、人は動きやすくなります。目標が明確になると、努力の方向性がはっきりとし、個々の行動に責任と自信が生まれます。さらに、具体的な成果が目に見えることで達成感や満足感が得られ、継続的な意欲やモチベーションを保つこともできます。
組織全体が具体的かつ達成可能な目標を共有すれば、チームとしての団結力や協調性も高まり、結果としてさらなる生産性の向上へとつながっていくのです。