最低賃金が上がることにあなたは賛成ですか?それとも反対ですか?

10月から最低賃金が、全国平均で31円引き上がることになりました。昨年の平均28円を上回る過去最大の引き上げです。
この最低賃金引き上げは、低い給料で働く人からすれば嬉しいことかもしれませんが、企業側からすれば大きな負担となります。
そうなると「給料は上がったけど、企業は人件費を抑えるためにリストラをして、逆に雇用が減ってしまうのでは?」ということが懸念されます。では実際はどうなのでしょうか。
最低賃金を上げたら雇用は減少する?
最低賃金引き上げにより高い給料を支払うことになれば、企業はこれまでと同じ利益を確保できなくなってしまいます。そうなると、効率化をはかるためリストラをしたり、海外の人件費の安い地域に生産拠点を移してしまうかもしれません。
これまでの経済学の理論としても、「最低賃金の引き上げ」すなわち「失業者の増大」ということで、一定のコンセンサス(合意)が得られていました。そのため、最低賃金引き上げに慎重な人は、このような主張をすることがよくあります。
しかし、昨年ノーベル経済学賞を受賞したカリフォルニア大学バークレー校のデービッド・カード教授らの研究結果をみると、一概にそうともいえなさそうです。
最低賃金を上げても雇用者数は減らなかった!
カード教授らは、アメリカのニュージャージー州と隣のペンシルベニア州という地理的にも似通った二つの州で、最低賃金に関する比較研究を行いました。
1992年までこの二つの州の最低賃金は全く同じでした。ところがニュージャージー州はそれまでの4.25ドルから5.05ドルに最低賃金を引き上げたのです。このときそれぞれの州による雇用者数がどう変化するかを、特殊な手法をつかって比較したのです。
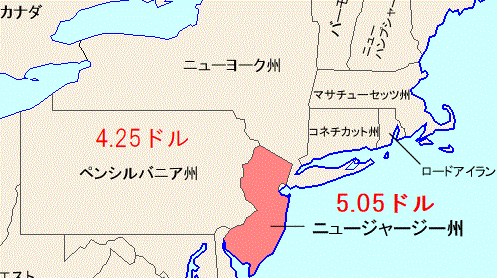
すると、最低賃金を引き上げたニュージャージー州の雇用は、これまでの経済学の通説とは異なり、むしろ若干増えていたのです。この研究結果は、当時の経済学者に大きなインパクトを与えました。
なぜ雇用は減らなかったのか?
ではなぜ通説とは異なり、雇用が減少しなかったのでしょう。その理由は「企業は最低賃金によるコスト増をリストラではなく、価格に転嫁することによって切り抜けようとした」ということだったのです。
もちろんこれはアメリカでの研究結果であって、現在の日本にそのまま当てはまるとはいえません。しかし「利益の減少分を人件費というコストカットにではなく、価格に転嫁した」という点は注目に値します。
ここからはあくまで私見です
ニュージャージー州で行われた価格への転嫁は、単なる価格改定でした。すなわち、価格上昇に伴いなにかしらのサービス向上や付加価値を増加させたわけではなかったのです。そうできた理由には、当時のアメリカの高い経済成長率が背景にありました。
そのため、いまの日本で同じように価格を上昇させても、おそらく消費者からは受け入れられないでしょう。
私たちが最低賃金上昇のためにやるべきことは、単に価格を上げることではありません。価格をあげるために、サービスや価値を増大させる、あるいは効率化をし労働者一人あたりの生産性をあげることなのです。
それは企業任せにするのではなく、労働者自身も自分たちの働き方を見直すべきなのです。企業はコストカットという安易な道を選ぶのではなく、労働者は賃金に見合った働き方をするのです。それがいまの日本に必要なことなのです。